
| 家族構成 | ご夫婦・お子さまひとり |
|---|---|
| 施工エリア | 愛知県愛知郡東郷町 |
| 建物概要 | 二階建て |
| 敷地面積 | 38坪 |
| 延床面積 | 26坪 |

そんな声にお応えして、ネイエで働くご夫婦の住まいをご紹介します。
小ぶりなスペースの中で実現した、こだわりの住まい。
おふたりがネイエの設計士として、
たくさんの事例を見てきたからこそ選んだもの。
たくさんの選択肢を知っているからこそ選ばなかったもの。
そんな、ふたりの設計士が暮らす自邸のご紹介です。
目次
地形や立地のデメリットも厭わない

ご主人は、小学生のころに自宅を建て替えた経験から建築の道へ。奥さまは、インテリアや家具への興味が高じて家づくりへ。そして、ネイエの世界観に共感し、それぞれが設計士として入社されました。

結婚後、名古屋市内のマンションで暮らしていましたが、お子さまが成長していくなかで自然に家づくりを検討されたそうです。

住まいが建つのは、最寄駅から車で10分ほどの住宅街。間口が細い通路の奥に土地が広がる「旗竿地」という特殊な形で、四角い形状の「整形地」と呼ばれるの対して「不整形地」と呼ばれています。

「一般的には選ばれることの少ない形状の土地ですが、私たちはそういった土地も積極的に検討しました」とご主人。

どんな土地であってもアイディア次第で理想を叶えられるー。設計士としての知識と自信は、家づくりの選択肢を無限に広げました。
限られたスペースの中でも「余白」をつくる

駐車場として使う細長い通路と、家を建てる場所を合わせて40坪もない土地。「目と手が行き届く、自分たちにとってちょうど良い住まい」「体になじむような親密なスケール感を大切に」と考えていたおふたりにとって、最良の場所でした。


石畳のアプローチにはご主人が整えた苔や手入れが行き届いた植栽が並び、家の横を通りすぎて奥まで進んだところに玄関があります。「森を散歩するようなイメージで、家に入るまでに長く歩くことで、気持ちを切り替える時間がとれるんです」

玄関ドアを開けると、靴を脱ぎ履きするスペースから一段上がったところに土間スペースが。玄関と同じ石が張られていますが、そこにはベニワレンとスツール、そしてお子さまのおもちゃが置いてありました。


「ここは特に用途を決めず作ったスペースでしたが、荷物を仮置きしたりストーブを置いたり、気兼ねなく使えるので、余白として残しておいてよかったです」」と奥さまが教えてくれました。


シューズクローゼットは、通気性のいい籐(トウ)=ラタンを素材とした造作で、少しの透け感がすっきりした見栄えと使い勝手を両立させています。

「家づくりの最中は、子どもが眠ったあとそれぞれが描いた設計図を見せ合っていました」と、ご夫婦ふたりのこだわりは随所に、決して主張することなく散りばめられています。
光と風を招く格子

1階は、視線の先では終わらず、見えない奥へと続いていく設計に。

また、玄関の側は回遊できるように設計されており ”行き止まりがないように見える” のが大きな特徴です。

「視線の一番奥になる部分に窓をつけて明るくしたり、少しだけ曲がって見せることで、広さと奥行きを感じさせる効果があるんです」

広さを感じさせる工夫は天井の高さにもありました。一般的な天井高が2.4メートルほどなのに対して、玄関まわりが2.1m、ダイニングは3m。あえて高低差をつけることで、視覚的に開放感を出しているそうです。

さらに、場所を取りがちなソファは置かず、壁を張り出して造作ソファを設置。


クッションを外すと畳仕様に変わり、一年じゅう快適に。

壁のニッチには、建築関係の本が並びます。

「ここで本を読んだり、子どもと庭の植栽を眺める時間がお気に入りです」とご主人。

奥さまは「私も、ダイニングで縫製や工作をしたり、コーヒーを飲んだりする時間が好きです」と微笑みます。

建築家アルヴァ・アアルトの 1960 年代のヴィンテージのダイニングテーブル。「もともとの感性や好きだと感じるものが似ているので、家づくりで衝突するようなことはそんなにありませんでしたね」とおふたり。
他にも、ハンス J. ウェグナーのYチェア、モーエンセンのラウンジチェア、チェストなど名作家具がバランスよく置かれています。



大きな窓の格子をよく見ると、ベイマツの木枠に直接網戸が張られていました。「こうすることで網戸を隠しつつ窓を開けることができるんです」


数々の素材や組み合わせの技を知っているからこその厳選されたアイディア。別の窓にも多彩な格子がデザインされ、時間ごとに変わる光や影を室内に投影しています。


他にも、虫ピンを使った壁掛けや天井から下がるモビールなど、小物まわりにもお手本にしたいポイントがたくさんありました。


1階と2階をつながりで考える設計

2階は家族の休息スペース。まだ小さなお子さんに配慮して、階段の角は少しだけ丸く削られています。

階段を上がって右の和室は、寝室や家事スペースとして使われています。壁に四角く切り取られた木の部分は「ラワン合板(ベニヤ)」と呼ばれる素材で作られた扉。引き戸を開けると、小上がりのようになった収納スペースが現れました。

「1階のダイニングの天井を高くしたことで、2階にはこんな形の納戸アイディアが生まれました。意外と中は広くて、立って移動することもできるんですよ」

寝具や衣類などはすべてここに。まるで隠し部屋のようにわくわくします。

一方で左の部屋は、将来的にお子さんの部屋にできるよう設計されているそうです。こちらにも小上がりがあり、いずれベッドスペースとしても使えそうです。
小上がりの下には引き戸式の大きな収納棚。「実は、この収納の中に1階のエアコンの配管が通ってるんです。配管を完全に隠すこともできたんですけど、何かあった時に壁を壊さずにメンテナンスできるようにしました」


限られた条件を活かしながら、人の動きや物の配置、そして見えない部分まで細やかに配慮されています。
住まいは、大切な選択を繰り返した賜物

「完璧な家を目指すのではなく、子どもの成長や、その時々のライフスタイルに合わせることのできる、柔軟で、懐の深い家にできれば良いと思っていました。そう考えると、普段お客さまにご提案している住まいより、ずいぶんラフに考えていた気がします」とおふたり。


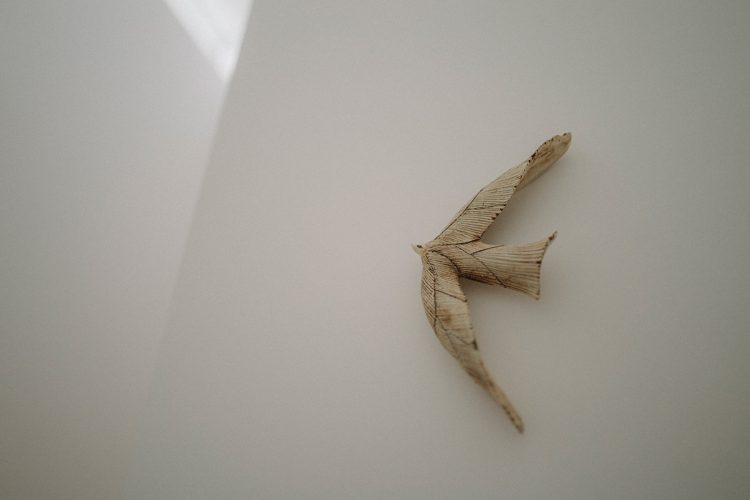
家づくりで一番大切にしたことを聞いてみると「芦野石や杉、い草畳などなじみのある自然素材を使うようにしました」と振り返るご主人に、奥さまも「漆喰の壁は、好きな絵や小物を飾ったときにイキイキとしているように見えます」と教えてくれました。

お気に入りの玄関⼾や

漆喰の壁

足ざわりが心地よい、杉の浮造り加工の床。


杉、芦野石、い草、ラワン、漆喰と、場所ごとにさまざまな素材を織り交ぜているにも関わらず、さりげなく見えるのはきっとバランスがとれているから。

「普段は何気なく暮らしていますが、旅行から帰ってきたときに家の中が木の香りで包まれているんです。ネイエは、接着剤がたくさん必要な新建材(化学建材)や壁紙をあまり使わないところが隠れたポイントですね」

「家の中にきれいな光が入ってくるだけで心がはずんで、 季節や天候、 植栽の些細な変化を感じるようになりました。子どもが空や植栽を眺めながらご飯を食べているのを見ると、とても嬉しい気持ちになります」


「小さい家」とおふたりは言いますが「本当に必要なものだけを大切に選ぶ」という考え方は、きっと多くの方の参考になるはずです。

住まう方々に、愛らしい時間を。そんな気持ちで、おふたりは今日も住まいと向き合っています。

ほかの暮らしも
覗いてみませんか?
-
#17
2025.08.08
余韻を愉しむ、美しい平屋の暮らし
控えめながら、確かなこだわりが住まいの隅々に息づいている住まいには、敢えて余韻を残すように設えたことで、暮らしの中にも静かな奥行きが生まれています。
-
#07
2024.08.02
歴史を紡ぎ旅するように暮らす
両親が残した土地に暮らすことを決意した奥さま。住まいのあちこちに置かれた家具や調度品は、代々受け継がれてきた貴重なものばかり。
-
#01
2024.02.05
窓から望む絵画のような庭がある家
シンプルな作りの中で素材にこだわり、飽きの来ないところがネイエの魅力。と語るお施主さまの暮らしぶりをご紹介します。
-
#15
2025.02.21
日々慈しむ暮らし
何気ない瞬間が思い出となり、重ねていく日常が静かに心を満たしていく。居場所によって見え方が変わる庭を中心とした平屋の住まいです。
-
#08
2024.09.06
ギャラリーがつなぐ平屋の暮らし
一緒に過ごす時間を大切にしながら、それぞれの個性はのびのびと。そんなご家族の暮らしぶりは、きっと多くの方のお手本になるはず。
-
#04
2024.02.05
家族6人がひとつながりとなる暮らし
夫婦とお子さま4人。ロフトを有する平屋に暮らすお施主さまご家族。家づくりを決めた理由は、コロナの流行がきっかけでした。

